- タイ深南部
ピース・メディア・デー・フェスティバルによせるメッセージ
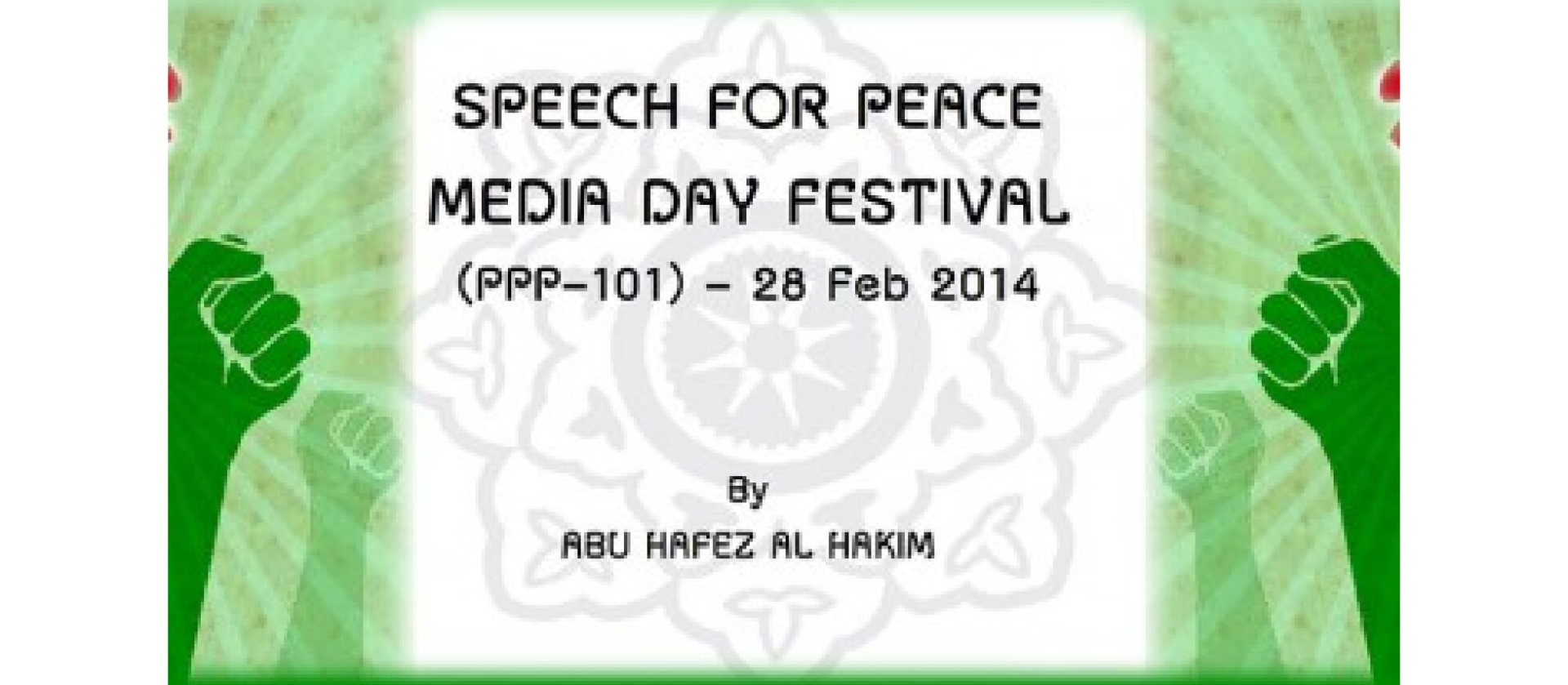
タイ深南部紛争:アブ・ハファス氏のスピーチについて
2004年に再燃したタイ深南部の紛争では、和平に向けて様々な取り組みが行われてきた。その結果、2013年2月、タイ政府と国民革命戦線(BRN: Barisan Revolusi Nasional[マレー語]、National Revolution Front[英])を中心としたグループとの和平対話が始まり、解決への期待が高まった。まず、2月28日、クアラルンプールでマレーシアのナジブ首相と会談したタイのインラック首相(当時)は、マレーシアをファシリテーターとしてBRNとの「対話」を開始すると発表した。そして、対話の開始に双方が合意する文書には、タイ政府代表のパラドーン国家安全保障会議事務局長(当時)とBRNの代表であるハッサン・タイブ氏が署名し、署名に際して両氏が行った歴史的な握手は、現地メディアでも大きく扱われた。
3月、4月、6月と行われた「和平対話」では、準備不足もあり具体的な進展は見られなかった。7月のラマダン(イスラムの断食月)の停戦も失敗に終わり、マレーシア政府を介した文章でのやり取りは続いていたものの、対話は再開されなかった。恩赦法案の国会提出を契機に始まったバンコクでの大規模な反政府デモ、解散・総選挙と選挙無効判決の大混乱に続き、インラック首相の解任、その後の2014年5月のクーデターにより、深南部の和平対話は完全に打ち切られたかに思われた。しかし、7月の段階で、ウドムデート国軍副司令官による発表で、マレーシアをファシリテーターとし、タイ政府代表として再び国家安全保障会議事務局長に返り咲いたタウィン氏とBRNを中心とした武装勢力との和平対話の継続が伝えられた。
以下の文章は、2014年2月に深南部パッタニー県で行われたピース・メディア・デー(Peace Media Day)というイベントで、武装勢力を代表してアブ・ハフェス・アル・ハキム氏がビデオメッセージという形で行ったスピーチである。Peace Media Dayというのは、タイ深南部で活動しているコミュニティーラジオやウェブサイトで情報発信している各種メディアが集まり、2月27日、28日の二日間、「10年の暴力、1年のパタニ和平プロセス(Ten Years of Violence, One Year of Pat(t)ani Peace Process: PPP101)」をテーマに開催されたイベントである。イベントでは、タイ国内外から招待された研究者、実際に深南部を担当している国軍の将校、和平対話でファシリテーターを務めているマレーシア元対外情報部長官ザムザミン氏なども参加し、深南部紛争の和平を考えるセミナーや討論会が行われた。対話のテーブルについたBRNを中心とするグループに近い立場のアブ・ハフェス氏のスピーチは、とくに武装勢力側の考え方に触れることができる貴重な文章であるため、本ウェブサイトに日本語訳を掲載することにした。

ピース・メディア・デー・フェスティバルによせるメッセージ
Speech for Peace Media Day Festival
Date of speech: 2014年2月28日
アブ・ハフェス・アル・ハキム
Abu Hafez Al Hakim
慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において
議長、来賓、講演者、そして来場の皆さん、
アッサラーム・アライクム、皆さんに平安あれ。
最初に、このように格式ある会場で開催されたピース・メディア・デー・フェスティバルにおいて、われわれパタニの闘士たちに意見を表明する機会を与えて下さった主催者の皆様に感謝申し上げます。これは重要な集いでありますが、パタニの闘士の声を聞かずして、こうした会合は完全なものとはなりません。われわれは長年、タイ深南部に暮らすパタニ・マレー人の民族性、信仰、土地の尊厳を守るため、辛苦に耐えながら闘ってきたのです。
まず皆さんにご理解いただきたいのは、パタニの紛争がこの10年だけの問題ではないということです。この紛争は、200年以上も続いている政治的、歴史的、社会的紛争です。つまり、パタニ・マレー人がタイ植民地主義のもとで味わった辛苦はパタニ地域の他の民族の人々、例えばタイ人仏教徒たちが2004年以降経験したものよりはるかに長い歴史をもつものだということです。われわれが闘っている相手はタイ植民地主義であり、タイの人々は敵ではありません。
次にご理解いただきたいのは、われわれが武装闘争という手段を選んだ理由が、タイ政府が人々の苦境にまったくもって耳を貸さなかったことにあるということです。われわれの過去の指導者たちは議会を通じて、あるいは人権侵害を訴える請願などによって闘ってきましたが、逮捕や投獄の憂き目に遭うことがたびたびありました。殺害された者もいますし、亡命した者もいます。悲しいことに、こうした状況は今も変わりません。
みなさん、パタニの闘士たちが和平プロセスに参加するのは今回が初めてではありません。現在進行中のクアラルンプール和平プロセスの前にも、非公式ではありますが、外国政府やNGOが仲介したプロセスがいくつかありました。しかし、それらは開始後すぐに頓挫してしまいました。例えば、ジュネーブ、ボゴール(インドネシア)、ランカウィ(マレーシアの島)などで行われたものがそうです。結局、計画がよくできていなかったり、準備が不十分だと、どんなプロセスも失敗するという教訓を残したのでした。クアラルンプール和平プロセスもまた、もし過去のプロセスの問題や弱点に対策を講じなければ、同じ運命を辿ることになるでしょう。
過去の和平プロセスは、秘密裏に行われ、交渉者の持つ権限が不明であったり、参加者が当事者をどれくらい代表しているのかといった疑問がありました。また、双方が異なるアジェンダをもって交渉にのぞんでいました。パタニの闘士たちの側は、タイ政府がどれだけ誠実か、また紛争解決にどれだけ真剣かということを見定めようというのを目的にしていましたが、タイ側は、情報収集という目的の他に、とりあえず暴力を終わらせる方法を模索しており、闘士側の代表者が現地の実行部隊をどれだけ統率できているかを見極めようとしていました。彼らを闘士としては認知せず、依然としてテロリスト扱いしていたのです。
クアラルンプール・プロセスはこれまでとは少し違っています。当初いろいろな議論を巻き起こしたとは言え、プロセスはオープンで、インラック・シナワトラ首相(当時)の公式の承認のもとでスタートし、タイ側は高いレベルの代表団(国家安全保障会議事務局長)を送り、マレーシアをファシリテーターとしていました。闘士たちは、国民革命戦線(BRN)のハッサン・タイブ師を代表者とする「国家と異なる思想及び意見を持つ人々」というように言及されます。これによって、パタニに関する和平プロセスは、初めて公式なものとなり、地域社会及び国際社会に受け入れられるものとなったのです。
2013年2月28日に締結された「対話プロセスに関する一般的コンセンサス」において闘士たちはタイ憲法の枠組みに「拘束される」とされたものの、われわれは、パタニ紛争の正義ある包括的で持続的な解決に向けて、武力闘争とは別な方法の可能性を求めて、交渉のテーブルについています。われわれは、対話と交渉を行うことによって暴力を減らす、あるいは完全に終わらせることができ、それがパタニの将来の地位を決定することにつながると信じています。
われわれの側にも、クアラルンプール・プロセスに懐疑的な者たちはいます。とりわけ、クルセ・モスク事件、タクバイ事件でパタニの人々の心情を踏みにじった者、すなわちかつてのタイ首相 1が関わっているという噂のために、そう疑う者がいました。しかし、それでもわれわれは招待に応えました。なぜなら、イスラムにおいては、たとえ敵からの申し出であれ平和の申し出は受けるべきだと教えられるからです。クルアーン戦利品章第61節は次のように述べています。「もし彼らの方で和平に傾くようなら、お前もその方向に傾くがよい。そしてすべてアッラーにお委せ申せ。アッラーは耳敏く、全てを知り給う。 2」われわれは一歩を踏み出しましたが、まだこれを疑い、様子見の構えでいる者もいます。
最初の2回の会談(2013年3月28日と4月29日)は、和平対話の基本的事項を議論しました。噂されたような、交渉や提案といったものはまったく何もありませんでした。最初の段階ではまずお互いの信頼の醸成に焦点を絞っていたので、内容は秘密とされました。しかし、タイのマスコミはこれに批判、糾弾を浴びせ、あるいは憶測に満ち、偏向した記事をかき立てて、「警鐘」を鳴らし始めました。タイ側の代表団もしばしば「誇張された」コメントを会議の前後に発しました。タイの指導者たちがみなそれぞれ自分の意見を表明したため、足並みが揃っていないことが露呈しました。こうした状況はプロセスの推進力を失わせたばかりか、プロセスそのものを危険にさらすまでに至りました。
そのため4月27日、プロセスのロードマップが不明瞭な中、BRNは「5項目の要求」を述べたビデオ・クリップをYouTubeに投稿しました。プロセスを正しい軌道に戻すことを狙ってのことです。われわれは「5項目の要求」を4月29日の公式和平対話で提案しました。しかし、タイ側は、実行部隊が暴力行為を減らすか停止するという点にしか関心がないようでした。そうしたタイ側の考えは6月13日に行われた会合で明らかになりました。彼らはその年のラマダン(イスラムの断食月)中の限定的停戦を提案したのです。BRNはいくつかの要求を加えて、タイ側の提案を上回る自主的停戦提案で応えました。
みなさん、このラマダン平和イニシアティブがその後どうなったかはすでにご承知の通りです。結局、われわれは、いかなるイニシアティブであれ、綿密に計画し、議論し、細部を確認し、双方が同意した上で実行されるものでなければうまくいかない、という教訓を学んだのでした。
このイニシアティブには多くの弱点がありました。信頼醸成措置を実行しないまま、拙速に進められてしまいました。双方が一緒に計画を練ったわけでもなく、議論もありませんでした。ファシリテーターが発表した7ページにも及ぶ「2013年ラマダン平和イニシアティブに関する規則」は、紛争当事者の了解を得た上でのものではなかったのです。それは公式合意などではなかったし、署名すらなされませんでした。したがって、当事者はいつでもそれに違反できるといったものだったのです。規則の違反を判定する審判員もいなければ、中立的な監視団もありませんでした。何より、規則や保護措置、いずれかが違反した場合の申し立て手続きについて、一般住民にきちんとした情報提供がなされませんでした。
ラマダンに入った第一週、極めて痛ましいできごとがありました。ある治安事件に関連して犯人と疑われた活動家たちが超法規的に殺害されたのです。これに対してBRNは交渉への参加を一時中断しました。そして8月6日、BRNの武装部門のメンバーが次のようなシューラ(諮問評議会)のメッセージをYouTubeに投稿しました。「この停戦はタイ政府自らが提案したものであるにも関わらず、そのために作られた規則を遵守していない。そのため、BRNは、タイ国会が5項目の要求を原則的に受け入れ、承認するまで、公式の会談への参加を中断する。」
8月終盤、タイ政府は5項目の要求のより詳細な解釈を求めてきました。これにBRNはファシリテーターを通じて38ページに及ぶ文書によって回答しました。しかし残念なことに、またしても、深南部の情勢は不安定となり、バンコクでの混乱が始まって、タイ側はなかなか返答をすることができませんでした。タイ政府代表団長の書面による回答は10月25日付けでなされましたが、その内容は「5項目の予備的要求はさらなる議論を行うにあたり受け入れ可能である」というものでした。
しかしながら、この回答はBRNの期待に応えるものではありませんでした。こちらは5項目の要求を「原則的に」受け入れること、そしてタイ国会の承認を取りつけることを求めていたのですが、いずれも満たされなかったからです。われわれは、もし5項目の要求が原則的に受け入れられたのでなければ、後になってひとつひとつタイ側が拒否するだろうと思いました。また、国家的アジェンダとならないのであれば、政権交代によって行方が左右されるだろうと思いました。
多くの人が、クアラルンプール・プロセスは失敗した、もう終わったとみなしています。そうした見方は、タイの政治的危機がこの先不透明だということ、また2013年12月1日にYouTubeで発表されたハサン・タイップ師がBRN代表団長を辞任したというニュースが影響しています。
しかし、忘れてならないのは、このプロセスは公式のものだということです。現在まで、BRNであれタイ政府であれ、ファシリテーターであるマレーシアであれ、いずれも公式のチャネルを通じて交渉から撤退するとの表明をしていません。したがって、プロセスは現在それぞれの都合により「中断」しているだけであり、すべての障害が取り除かれれば再開されるものです。
われわれ、パタニの闘士は、今のプロセスを今の代表メンバーで継続することに、引き続きコミットしていきたいと思います。今後、プロセス参加者を随時増やして行きます。それによって、代表団はパタニのあらゆる層を代表する「パタニ・マレー・コミュニティ」というものになっていくでしょう。
われわれは職業、背景、民族、宗教に関わりなく、すべてのパタニの人々に情報や議論を提供し、平和は万人にとってよきものであるということを伝えたいと考えています。NGOやCSO(市民社会組織)の平和を支える活動は妨害されてはならず、彼らがハラスメントを受けることがあってはなりません。タイ政府には、すべてのパタニの人々が、暴力に訴えることなく、彼らの生活の真の利益のために、自決権あるいは「独立(merdeka)」についても、自由に意見を表明できるような真の民主主義を実現していただきたいと思います。いかなる政府であれ、自らの国民に対しては弾丸や爆弾ではなく、言葉で考えを伝えるというのが賢明なやり方であります。また、われわれにとっても、たとえ10年、15年かかろうとも、今平和を語る方が、これから先20年、30年闘い続けてやっと和平の途にたどり着くことになるよりも、賢明であると考えています。
われわれは、「国家と考え方・意見を異にする人々」であるパタニの闘士たちが、パタニに無事帰還でき、同胞及びタイ住民に語りかけることができるよう、政府に要請します。パタニの闘士の代表が、タイ国会においてすべてのタイ国民に対して発言する場を与えられ、われわれが求めているのは正義と自由に他ならないということを伝える、そういう名誉ある日が到来することを、心待ちにしています。
最後に、故ヤセル・アラファトパレスチナ解放機構(PLO)議長が1974年11月13日に国連で行った演説の一節を引用したいと思います。
「今日私は片手にオリーブの枝を、もう一方の手に自由の戦士の銃を持ってきた。どうか私の手からオリーブの枝を落とさせないで欲しい。」
そして彼は次のように結論しました。
「戦争がパレスチナで起きた。そしてパレスチナで平和が生まれようとしている。」
これと同様に、私は次の言葉で締めくくりたいと思います。
「今日われわれは武器をもたず、平和の象徴としてハイビスカスの花をもってきた。戦争がパタニでも起きた。そしてパタニで平和が生まれようとしている。パタニ・ダルッサラーム(平和の地パタニ)として知られるこの土地で。」
ワッサラーム・アライクム。皆さんに平安あれ。
ありがとうございました。
アブ・ハフェス・アル・ハキム
(パタニの塀の外にて、対話のテーブルについたパタニの闘士たちを代表して)
Read the original speech in English here: http://www.deepsouthwatch.org/node/5389
Download a PDF of the original speech in English HERE

編集委員、上智大学アジア文化研究所客員所員







