- タイ深南部
タイ和平会談を理解する

今年[2013年]2月、タイ政府が南部国境地域における暴動に歯止めをかける試みとして武装勢力との和平交渉に乗り出すとの発表がなされ、歴史的な躍進であるとして広く支持された。、現実はもう少し複雑だということがやがて明らかになるであろう。イスラム教徒住民が大半を占めるタイ南部国境地域では今も反政府活動が続いており、2004年以降死者は5,300人を超え、2004年から2007年には、イラクとアフガニスタンに次いで世界でもっとも激しい紛争であったとされている。
今回、タイの関係当局がかねてよりマレーシアにいる武装組織に働きかけていたことが、遅ればせながら発覚した。確かに最初の数回にわたる公式対話は、マレーシアのマハティール・ビン・モハマド元首相の招集によって、ランカウイ島において会談が実現することとなった。会談にはタイの当時の国家安全保障委員会の委員長をはじめ、タイ政府の高官が出席している。タイ王国ランカウイ総領事館の名誉領事シャズリル・エスカイ・アブドラ(Shazryl Eskay Abdullah)が、マレーシアの元警察長官とともにファシリテーターを務めた。クアラランプールの政府関係者はこれらの会談の報告は受けていたが、マレーシアの現役官僚や政府関係者は一人も立ち会っていない。一方、当時タイ政府から紛争の対策を提言する命令を受けて国民調停委員会(NRC)の委員長を務めていたタイのアナン・パンヤーラチュン元首相も会談に参加している。その他には、武装組織であるパタニ共和国革命戦線(BRN)、パッタニ・イスラム・ムジャヒディン運動(GMIP;Gerakan Mujahideen Islam Pattani)およびパタニ連合解放組織(PULO)からの代表者らや、今は消滅したベルサトゥ(ベルサトゥは統一の意;PULO、一部のBRN、GMIP関係者の間で形成された緩やかな政治的連合体)の元指導者ワン・カディル・チェマン(Dr Wan Kadir Che Man)などが参加者として名を連ねている。
しかし、タイのタクシン政権はマハティール元首相の取り組みをほとんど無視した。2006年9月の軍事クーデターへと発展した広範な国内の政治危機への対応に気を取られていたためである。アナン[元首相]自身から聞いた話だが、ランカウイ島で会談した武装組織の代表たちは、自治権といった政治的な解決には一切関心がなく、ランカウイでの話し合いは真剣な交渉への足がかりというよりも、せいぜい信頼醸成措置程度のものでしかなかったとのことだ。
交渉における3つの問題点
それ以降、いくつかの対話プロセスがあった。インドネシア政府の仲介により行われた2008年のボゴール会談、2009〜2011年のアピシット・ウェーチャチーワ政権の最中に盛り上がりを見せた、2つのヨーロッパの組織によって現在まで続けられている取り組み、イスラム諸国機構による2010年の施策、民政機関であるSBPAC(南部国境県行政・開発センター、Southern Border Provinces Administrative Centre)のサポートを得て、亡命したタクシン元首相が行った2012年の私的な外交などである。
こうした対話の試みはすべて、同じような壁にぶつかってきた。第一の問題は、誰がタイを代表するか、ということである。「国家」としてのタイは決して単一の主体ではない。南部の紛争は、互いに競い合ういくつかの団体や機関の管轄下にある。理論上は首相と内閣が問題の責任者であるが、これは実際には張り子の虎のようなもので、戦略立案のほとんどを国民調停委員会が担ってきた。同時に、建前の上では、民政機関SBPACに主導権が委ねられているにもかかわらず、タイ王国陸軍がしばしば深南部で植民地領主のように振るまっており、2006年のクーデター後に多くの権限と資源を与えられた冷戦時代の上部組織である国内治安維持部隊(ISOC)を通じて特別予算を独占している状態である。選挙で選ばれた政治家たちとしのぎを削る官僚組織との間に、激しい不信感が存在する。ある特定のパートナーが「所有する」対話プロセスを、浦では他のパートナーたちは認めていないというケースが多い。
2つ目は、一体これらが何についての対話なのか、というきわめて単純な問題である。この紛争は、本質的には政治の問題である。大半の住民がイスラム教徒でマレー語の方言を第一言語とする地域において、タイ国の正統性は弱い。ところが歴代政府は、ドラッグや密輸や犯罪などの問題を挙げては、延々と言葉を濁して武装勢力の大義である政治的本質を認めようとせず、自治権その他の地方分権のあり方について真剣に、一貫して取り合うことを避けてきた。政府側の度重なる不誠実な対応を考えれば、武装組織が実質的な話し合い(タイの安全保障当局者は、「対話」こそが武装勢力の指導者を特定・制圧する主たる手段であると考えている)に参加することを期待する方が無理であろう。
第3の問題は、誰が武装勢力を代表するか、ということである。武装勢力内に、数名のリーダーたちのグループが地域の小集団に対して実質的な権限と支配を有する「パタニ・マレー民族革命戦線コーディネート(BRN-Coordinate)」として知られる、団結したトップダウンの組織があり、タイの関係当局はなんとかして武装勢力をBRNコーディネートとして一括りにしたがっている。だが、juwae (若い戦闘部隊)は分散しており、さまざまなグループや年長世代のリーダーたちとのつながりや忠誠関係も持ち、彼らが簡単に停戦に応じたり、また彼らを紋切り型の提案によって囲い込むことはできないと、多くのアナリストたちは見ている。一連の対話のほとんどが、マレーシアなどに拠点を置いて活動しているjuwaeとはほとんど関係のない、自称「分離派の指導者」らとの間で行われてきた。北アイルランド独立運動におけるIRA暫定派やシンフェイン等など、他の紛争における武装組織と異なり、タイ南部で頻繁に戦闘を繰り広げる集団は、自分たちを代表して交渉を行うことのできる純粋な「政治部門」を持っていない。

新たな展開か?
2月27日の発表の何が目新しかったのか。タイ、マレーシア両国の現職の首相が直接関与したことは著しい進展であり、高位高官がより積極的に問題に取り組むであろうことが示唆された。インラック首相は2011年半ばに就任して以来初めて、南部問題を最優先課題にすると表明した。タクシン元首相に近しいとされるNSC事務局長パラドン・パッターナーサ陸軍中将(Paradorn Patthanatha-butr)との公の場での調印式もまた、前例のないことであった。2週間後にさらなる会談が行われるとしたマレーシアのナジブ・ラザク首相による声明は、これがいろいろな意味で重要な契機であると思わせた。ナジブにはどうしても事態を進展させたい事情があった。与党の実績が振るわず首相の立場も相当に弱体化している中、5月5日に非常に厳しい総選挙を控えており、好意的な報道を大いに必要としていたのである。
しかし、ほかの側面において今回の新しいタイ南部対話は、以前に6回ほど行われた対話と似通っている。タイ国軍が対話に参加しているという証拠はなく、陸軍司令官プラユット・チャンオチャ(Prayuth Chan-ocha)は懐疑的な姿勢をはっきりと示した。政治的な解決策が用意されているというような兆候も明らかではない。今後の話し合いのオプションについて、政府の見解も機関によってばらつきがある。南部紛争の安全保障問題を統括する任を与えられたチャルーム・ユーバムルン(Chalerm Yubamrung)副首相は、ことさら無駄な動きをしている。メディアに向けた副首相の、歯に衣着せない声明は、しばしばバンコク政府による意図的な妨害作戦のようにも聞こえる。
9人で構成されるタイ政府チームも事前準備をほとんどせず、明確な統一見解も持たないまま会談に臨んでいる。チームの3本柱はパラドン[NSC事務局長]、南部国境地域行政局長官であるタウィー・ソドソン(Tawee Sodsong)、そして国防省副事務次官のニパット・ソングレク大将(Nipat Thonglek)である。ISOC高官のナカロップ・ブンブアソン少将(Nakrop Boonbuathong)は、軍部の目となり耳となって、陸軍司令部に対話の進展に関する情報を逐一報告している。また、チームにはイスラム系市民団体の指導者とパタニ在住の仏教研究者も名を連ねており、交渉プロセスの信頼性向上の一翼を担っているが、彼らの交渉における厳密な役割は定められていない。

恐らくもっとも深刻な問題は、合意文書に調印した一匹狼、BRN「指導者」ハサン・タイブ(Hassan Taib)に、そもそもこの和解を遂行することはおろか、交渉する立場やコネクション、そして権限があるのかという点だ。1960年に設立されたBRNは、かなり前から3つのグループに分裂している。6人で構成されるBRNチームは会談の開始以降メンバーの入れ替えが行ったが、組織の主要な顔ぶれは交渉の場には出てきていない。ハサン・タイブの会談への参加はマレーシアのSpecial Branch(秘密警察)がお膳立てしたもので、長くマレーシアに在住してきた反政府グループのメンバーたちは、対話プロセスに参加する以外に選択肢がなかったのではないかという憶測が飛び交っている。言い換えれば、これは自主的、自発的なプロセスではなく、マレーシアが自国の利益のために画策したことらしい。
それでも、Special Branchの役割は時間とともに縮小され、会談も一人歩きを始めている。BRN代表団は、2回目の会議で主導権を握るべく5つの要求事項リストを提示した:1)マレーシアを調停者として認めること、2)公安犯罪で収監されている者たちの釈放、3)逮捕状を取り下げること、4)マレー系イスラム教徒の「パタニ」の所有者としての権利を認めること、5)BRNを解放運動と認めること。このリストからは一定の計画性と先見性がうかがえ、準備不足のタイ側代表団は不意打ちを食わされ、バンコク政府は対応に四苦八苦することとなった。
…それともさらなる課題か?
この和平プロセスにおける大きな問題は、根深く分断されて機能不全に陥っているタイ王国の内政が色濃く反映されており、それが南部紛争への対応に大きな障害となっているという点である。アピシット政権は国際NGOを関与させてのジュネーブ・プロセスを打ち出していたが、インラック政権はその取り組みから離れ、亡命したタクシン元首相が進めるプロセスを推す構えである。パラドン[NSC事務局長]、タウィー[南部国境地域行政局長官]およびニパット[国防省副事務次官]は、タクシンと(クアラランプール会談の最中にも)定期的に連絡を取っており、ドバイからのメッセージや電話を受けているとされる。数多いる反タクシン派や批評家たちは、タクシンの首相在任中(2001〜2006年)に反政府活動が劇的にエスカレートしたことは多少なりとも元首相の責任であると考えており、和平プロセスにタクシンが関与することでますます懐疑的な目を向けるであろう。
紛争に対するタクシン自身の考えを確認することはなかなか難しい。2008年にタイを出国して以来、元首相の態度はますます気まぐれになり、先頃行われたアメリカ人ジャーナリスト、トム・プレートとの、本一冊分にものぼるインタビューの中では、2004年10月のタクバイ事件において、武器を持たない抗議デモ参加者が78人も死亡したことをマレーシアの責任にしようとしている。だが、時折、奇妙な陰謀説を持ち出すものの、多くの命を奪った暴力的な紛争への打開策を見いだす手伝いを自分がすれば、自らのイメージの回復につながり、いずれタイに戻るための足がかりになると決意したようでもある。
しかし、クアラランプール和平会談を批判する者の中には、プロセスにおけるタクシンの役割に対する根深い疑念を持つ者も多い。2004〜2005年の手荒なやり方があまりにも扇情的であったことを考えれば、確かにタクシンは仲裁役としてはもっとも不適任であるかにように見える。だが、交渉人たちを「チーム・タクシン」として見限ってしまうことは不当で短絡的すぎる。北アイルランド問題の解決においてトニー・ブレア[元イギリス首相]が示したように、どうにも手に負えない紛争の突破口が、時として並外れた自信を持った政治家たちによってもたらされることもあるのだ。
翻って、日々激しい攻撃を繰り返す多くのjuwae (若手戦闘部隊)は、自分たちの苦闘と大きく乖離した和平プロセスには心を動かされていない様子だ。また、会談を大げさなまやかしだとする見方が大勢を占める学生や青年運動家たちの間でも支持されていない。直近の対話が始められて以降、軍と民間人の両方を標的として数多くの猛攻撃が行われており、今のところ何ら合意に達していないということをまざまざと見せつけるかのようだ。
しかし、紛争地域にいる643人のイマーム(イスラム教指導者)全員からの連絡を受け、6月13日に行われた最後の会談において、交渉人たちが現地の暴動に影響力があることを示す善意のしるしとして、BRNはラマダン期間中の部分的あるいは全面的な戦闘中止に同意した。今後の行方は、いまだ具体的な結果を生んでいないプロセスに対してかなり懐疑的なバンコク市民が見守る中、本当に約束通り戦闘中止が守られるか否かにかかってくる。戦闘を減らすのに役立つ対話であれば何でも歓迎という状態ではあるが、タイ南部和平への取り組みを真剣に進展させたいというのであれば、双方からもっと深い関与が求めらていれる。
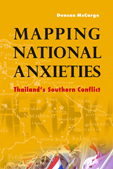
リーズ大学の東南アジア政治学教授で、コロンビア大学の客員研究員。タイ南部の紛争に関する著書にRethinking Thailand’s Southern Violence (ed., NUS Press 2007)、Bernard Schwartz賞受賞作Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand (Cornell 2008, Thai translation Kobfai 2013)、Mapping National Anxieties: Thailand’s Southern Conflict (NIAS 2012)などがある。

『P’s Pod(ピースポ)』に掲載されている論文・記事は、指定のない限り、著者本人の個人的な意見や見解を反映したものであり、著者の所属する役職や組織、または特定の組織、団体やグループなど(著者及び編集委員会を構成する大学等も含む)の意見や見解を反映するものではありません。







