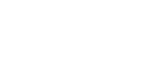事業内容
ロシアにおける日本研究やアジア研究、また日本におけるロシア研究に携わる人材は、両国ともに不足しています。特にこれからの時代に日ロ両国をアジアの多国間関係のなかでとらえる専門家が必要であるとの問題意識から、笹川汎アジア基金では、ロシアと日本およびアジアの関係について政策的思考をもった研究を担う次世代の専門家育成を目指し、同地域における若い世代の研究者が相互交流を深めながら研究能力を高めるための活動を支援してきました。
2004年10月からの3年間の事業計画で、北海道大学名誉教授で拓殖大学海外事情研究所教授(当時)の木村汎氏を主査として、日本におけるロシア研究のベテラン5人と若手研究者8人、計13人から成る研究チームを結成し、ロシア、中国、米国からの講師を迎えて、現代ロシアをめぐる国際関係を英語で討議する国際セミナーおよび月例研究会を開催しました。また、日本の若手研究者が海外のロシア研究者や国際関係の学者と国際的な場で討議する経験を積むため、第7回国際ロシア東欧学会世界大会(05年7月25~30日、於ベルリン)への派遣など、国際会議における研究発表や、海外での調査研究を支援しました。
本年度は、国際会議「北太平洋学術交流会議:ロシアの対アジア諸国関係を中心に」(06年10月18、19日、於札幌・北太平洋地域研究センター)に若手研究者が参加し、米国ブルッキングス研究所世界経済・開発センターのクリフォード・ガディ上級研究員、モスクワ国際関係大学のセルゲイ・チュグロフ教授ほか、中国、韓国のロシア専門家計15人と討論したほか、英国キングスカレッジでの国際ワークショップ(07年2月26日)に若手研究者2人を派遣し、ヨーロッパとアジアからみたプーチン政権下のロシアについて意見交換しました。また、研究会メンバーの論文集『アジアに接近するロシア』(日本語版)を北海道大学出版会から出版し、『Russia's Shift Toward Asis(英訳版)をオンデマンド出版しました。
ロシア研究の停滞というグローバルな偏向を背景に、中長期的な視野で国際関係の全体像を踏まえてロシアを分析できる若手研究者の存在が重要であるという認識は、3年間の事業のなかで協力を得た海外の専門家の多くが共有していました。本事業を通じて培われた国内外の専門家のネットワークが、今後の日本人若千研究者の活躍においてもリフースとしてつながっていくことが期待されます。
| 事業実施者 |
笹川平和財団
北太平洋地域研究センター(日本)
|
年数 |
3年継続事業の3年目(3/3) |
| 形態 |
自主助成委託その他 |
事業費 |
15,340,165円 |