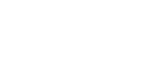事業内容
本事業は、日本、アメリカ、カンボジア、ラオス、ベトナム、タイの大学が共同で、学生たちの相互理解を図るとともに、東南アジアの農村コミュニティへの理解を喚起することによって、広い視野を備えた人材を育成するために行われてきました。
このプログラムでは、まず東南アジアに関する知識を深めるため、日米の学生を対象とした第一オリエンテーションを名古屋地域のNGOの協力を得て行い、その後、チェンマイで、カンボジア、ラオス、ベトナム、タイの参加学生、教授陣と合流して、第二オリエンテーションを行うという日程が組まれました。
チェンマイ大学における講義とフィールド観察で、東南アジアの農村コミュニティに関する知識を得た後、学生たちは国籍の混合するグループに分かれ、3週間ほどの日程で農村コミュニティ活動に参加し、フィールド調査を行いました。このフィールド調査は生活文化、保健衛生、農業、教育、環境問題、ミクロ経済と生活改善という点に関して行われました。調査結果は、その後の評価活動の際に、個人レポートならびにグループ・レポートという形で発表され、各レポートの内容について意見交換を行って事業全体の総括としました。
1997年度は、7月にカンボジアで政変があったため、実施時期を4か月ほど遅らせ、97年12月から98年1月にかけて、チェンマイを中心とするタイ北部地域でフィールド調査を行いました。
本年度は、98年7月末にチェンマイでオリエンテーションを行った後、メコン川をさかのぼってラオスのルアンプラバンに入り、周辺の7村落で3週間にわたるフィールド活動を行いました。多国籍のグループ編成による農村コミュニティ活動を通して、学生たちは相互の理解と、東南アジア、中でも農村の生活について体験に根付いた理解を深めました。
日米の学生はもとより、これまで自分たちの生活圏から出たことのなかったカンボジア、ラオス、ベトナム、タイの学生が、自国の発展状況と問題点、さらには近隣諸国の現状に対して正しい認識をもつ機会を得たという点で、当事業は成果をあげました。また、日本ではNGOがさまざまな角度から当事業を支え、これがNGO活動の活性化につながりました。
| 事業実施者 |
東海アジア太平洋地域開発研究所
|
年数 |
2年継続事業の2年目(2/2) |
| 形態 |
自主助成委託その他 |
事業費 |
2,425,036円 |