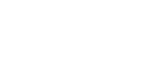事業内容
本事業は、日本の南九州地方がもつ畜産公害処理などの環境技術を、ミャンマーの少数民族(シャン族)居住地域であり、同国の中でも特に貧困地域であるシャン州南部流域に移転し、同地域の環境改善に役立てようというものです。同時に、合鴨農法などの独自手法の指導と技術移転により、同地域の農業開発にも役立てます。
2000年度は、昨年に引き続き日本人専門家6人がミャンマーを訪ね、合鴨農法、地域循環システム農法などの独自農法について、シャン族農民を対象に講習を行いました。1998年の事業開始直後から日本人専門家による直接指導を受けた村は6カ所にのぼります。それらの農法の採用により、ジャガイモの収穫量が以前に比べて5倍に増えるなど、目に見える効果も出ており、近在の村々にも、日本人専門家の来訪を心待ちにする雰囲気が醸成されています。
一方、ミャンマーからは第3期目の研修生4人が日本を訪れ、日本語のほか、しいたけ栽培や、芋づくり、林業などの基礎を学びました。事業開始以降、日本で研修を受けたミャンマー人は合計8人(半数は農業従事者、半数は林業省職員)となりました。そのうち9 8年度、9 9年度の研修生4人については、すでにシャン州で指導的な役割を果たしていることが確認されています。
0 0年度の研修生4人についても、帰国後の活躍が大いに期待されるところです。
本事業はもともと、日本人農業専門家のミャンマー派遣とミャンマー人農業研修生の日本受け入れに限った支援でしたが、これが呼び水となってさまざまな関連プロジェクトが企図されました。現実となったものだけでも、日本政府によるシャン州農業研修センターの建設、国連による麻薬代替作物振興事業、カラモジア独自の現地小学校建設、九州電力による林業振興事業、風力発電事業など、実にさまざまな分野に及んでいます。特に、日本政府によるシャン州農業研修センターの建設は、同センターが本事業による研修の場所を提供してくれたことで、政府支援と民間支援との融合という意味でユニークな試みとなりました。
99年には中学生だけの「スモール・ミャンマー」というN G Oが鹿児島に設立されるなど、地域対地域の交流という副次的効果がさらに進みつつあることも見逃せません。本事業で鹿児島を訪れた研修生が県内の中学校で講演をしていることや、事業そのものが地元マスコミで取り上げられたことが大きく影響しています。
| 事業実施者 |
財団法人カラモジア(日本)
|
年数 |
3年継続事業の3年目(3/3) |
| 形態 |
自主助成委託その他 |
事業費 |
5,600,000円 |