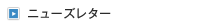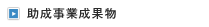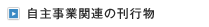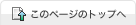レポート・エッセイ
公益法人制度改革の現状と問題点
入山 映
- 本レポートは全国公益法人協会発行
- 「「月刊 公益法人」第35巻 第2号(平成16年2月号)に掲載された。
はじめに
平成15年6月27日「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(以下「基本方針」という)が閣議決定された。100年ぶりの民法改正に初めて言及した平成13年の中間法人法の付帯決議から2年。その後に閣議決定された「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」の方針を受けて、平成14年8月に内閣官房行政改革推進事務局が政府行政改革推進本部に「公益法人制度の抜本的改革に向けて(論点整理)」を報告し、発表してから1年である。「玉虫色(注1)」 だとも評される文書だが、その評価については後に触れる。
さてこの間、制度改革の議論とは別に、平成14年には税制調査会が非営利法人課税ワーキンググループを設置。税制面の議論を重ねているのは周知とおりである。議論の経緯はウエブ上に公開されている(注2)ので読まれた方も多いと思う。
制度そのものと、税制上の措置の話は本来別物である。しかし、これまでの公益法人制度が両者を表裏の関係として扱っていたこと、それが100年間続いてきたという歴史的な経緯、さらにはその間に醸成された制度の社会的意味や機能についての思い入れなどから、本来異なった次元で議論されるべき様々な意見が同じ平面でぶつかりあい、やや議論が混迷した観があるのは否めない。その辺りをいささか解きほぐしてみようというのが本稿の意図である。
何が問われているのか
迷走したやに見受けられるこの間の議論の委細は割愛する。しかし、その背景や雰囲気、さらにはその持つ意味、つまり「公益法人改革」では一体何が問われているのか、についてのおおよその問題意識は以下のようなことになる。
まず平成12年のKSD不正経理事件に端的に現れたように、不祥事・伏魔殿・何やら疑わしい公益法人、というイメージには拭い難いものがあった。この先入観ともいうべきものが、増幅する傾向にあるか否かは定かでない。が、「改革」の声の背景には、それが依然牢固として存在したといってよいだろう。
その反面、平成10年の特定非営利活動促進法によって成立した通称NPO法人は、清く正しく美しいとは言わないまでも、公益法人とは異なったもの、公益法人ごときと同一視されたくない、「巻き込まれ(注3) 」ては迷惑、という意識も一部にではあるが垣間見られるようになる。
さらに、「公益法人改革」が行政改革推進事務局によって所管されたことが、この「改革」の受け止められ方を象徴的に示しているであろう。事実、事務局が最初に取り組んだ課題が「行政委託型公益法人」であった。つまり、官と癒着した「官益」法人、あるいは天下りを含む「蜜の味」、征伐・退治されるべき存在といった公益法人像にもこれまた抜き難いものがあったのである。新聞紙上に公益法人名が報道される時、某々省庁の「外郭団体である」ナントカというケース(注4)が圧倒的に多いのは、この間の事情を問わず語りにしていると言ってよいだろう。さらに「蜜の味」と言われるものが、単なる税金による天下り先の確保という意味を超えて、税制上の優遇措置を利用しながらぬくぬくと営利企業まがいのことをしている、という疑念にまで発展する。
何やら怪しげな、お役所べったりの、税金を浪費する、そんな存在がなぜ許されているのか。これには徹底的にメスを入れるべきだ。これが公益法人改革の名の下に問われているかに見えた。
真に問われるべきは何か
しかし、何故そんなことが起こるのか。公益法人は、主務官庁が厳重に審査したうえで「許可」したものに限って設立が認められるのではないか。そのうえ、設立後も主務官庁の煩瑣極まりない「指導監督」に服することを余儀なくされる。結果、公益法人の主体性とか、ガバナンスはほとんど存在しない状態に陥る。「それでも」起こる不祥事は、許可と裏腹になった指導監督体制が全く機能していないことを意味する。それどころか、これら諸悪の元兇は、いわば十手と捕り縄を一緒に持たせている許可制度とそれに伴う指導監督体制にあった、と言ってもよい位のものである。
ところが、(ここから先が、前に述べた議論の混乱に連なるのだが)これまでのところ許可制度・指導監督体制については、その無力さ、あるいは有害さについて指摘する声よりは、次のような見解が支配的であった。
そこまで厳重に責任ある官庁が監視しているの「だから」、そうした法人に対しては税制上の優遇措置を与えても構わない。それどころか、カテゴリカルにある範疇の法人に対して税制上の優遇措置を与えるためには、優遇の要件に関して国家公権力(の機関としての官庁)の判定が必要である。という議論まで出てくる。関係者、特に税務当局者から見れば、これは大変便利な理屈であった。個別の収益事業に関する課税と異なり、活動実態についての判断はほとんどしなくてよい。公益法人側にとっても、一旦設立してしまえば自動的に付与される優遇措置であり、後に触れる特定寄付を巡る煩瑣な手続に比べればほとんど別世界であった。だから、何らかの特性を持ったグループを取り出して、それをひとまとめにして扱いたい、という思いは、同床異夢ではあるものの、今なおあちこちに支持者が多い、ということは指摘しておいたほうがよいだろう。
問題の整理
ここで錯綜しているかに見える議論の整理を試みると、とりあえず論点は4つに分かれていることが解る。
その1は法人設立に当たっての許可主義と、それと表裏一体の関係にあった指導監督体制の問題である。
その2は、法人法定主義を採るわが国の法体系の中で、これまでの「公益法人」に代わるものが必要か否か。必要ならばどのような法人類型を構築するかという問題。
その3は、どのような活動を営む法人に対して、どのような税制上の優遇措置を講じるのか。その理由は何かという問題。
そして最後に、既存の公益法人の中で、如何かと思われる存在はどのようなもので、それをどのように淘汰するかという問題。さらには将来にわたり、そのような存在の発生を阻止することは可能か、という問題である。
このそれぞれについて、冒頭に触れた玉虫色の「基本方針」がどう取り扱っているか、扱っていないかにも言及しながら見てゆくことにしたい。
許可主義
まず、許可主義と指導監督体制が諸悪の根源であったことについては、さすがに異論がないように見受けられる。「見受けられる」などと奥歯に物の挟まったような言い方をするのにはわけがある。
許可主義の弊害を認め、準則主義による非営利法人制度を作るべきことは「基本方針」の中に明記されている。これは識者によって指摘されて久しく、今回抜本的改革に際して明確に方針が打ち出されたことは一大進歩である。が、準則主義によって設立された非営利法人のうち、公益性を持つ活動をするもの(いわゆる二階部分。つまり準則主義によって自由に設立される法人(一階)のうち、税制面を中心として何らかの特別な取扱いを受けるべきもの)について、その判断基準と判断主体は別に「検討する」とされる。
判断基準は「客観的で明確な」ものであることを要求しているから、さすがに事実上の許可主義の復活はないにしても、注意していないと、実際の活動内容の判断を巡って、主務官庁による指導監督体制の復活は十分に可能である。仏作ってなんとやら。これが復活したのでは、何のための準則主義が解らなくなることの認識が肝要だろう。
勘ぐりが過ぎるようにも受け取られるかもしれないが、根拠がないわけではない。というのも、準則主義というのは登記だけ、つまり形式要件だけで設立できてしまうから看板と中身が違うことは十分にあり得る。「公益のために」設立しました、と称しても、実際の活動がそのとおりである保証はどこにもない。だから、税制上の優遇措置を含む何らかの特別な取扱いをすべき法人(の活動)については、誰かがどこかで別途判断をしなければならないという問題は常に残る。これが、事後に要件を欠いたものを見付けて、それなりの対応をすればことは済む、という考えではなく、悪いことをしないように、できないように予防したい、しなければならない、というメンタリテイと結び付くと、かの指導監督体制の復活は現実の危惧となるからだ。
法人類型
これは、準則主義によってどのような法人類型を創設しようとするか、という第二の問題にも関わってくる。「公益性の有無に関わらず新たに非営利法人制度を創設する」のであれば、新法人制度が中間法人、NPO法人はもとより、100を超える法律によって成立している学校法人や社会福祉法人、宗教法人などを含むものとなり得るのは当然である。「なる」ではなく「なり得る」と言ったのは、今回改革対象になっているのは公益法人、つまり民法34条の財団・社団のみであって、それ以外の法人は対象にしていない、という考え方があるからだ。「基本方針」が玉虫色だという理由の1つはここにもある。現行制度が法人格取得と公益性判断・税制上の優遇措置が一体となっているからよくない。だからこれを分離し、公益性の有無に関わらない新非営利法人制度を作る、と言いながら、現行の中間法人・NPO法人との関係は「整理する」と述べるにとどまる。
これが先に述べた「あんなものと一緒にされてたまるか」みたいな動きや、その他諸々の要素(注5)の結果であることについては詳論しない。それはともかく、これからどうするかという話になると、3つの考え方がある。1つは極力「非営利法人」を広くとって、できるだけ多様な法人をこの傘の下にまとめてゆこうというものである。例えば、営利社団法人に株式会社や有限会社等など多様な類型があるのと同じように、非営利法人に括れば、その中は色々あってよいではないか、という立場(注6)である。いま1つは、既存の様々な法人類型はそのままにしておいて、とりあえず狭く民法34条の公益法人についてのみ、あるいはどんなに拡大しても中間法人・NPO法人の3つだけを対象として法制度を考えるというもの(注7)である。民法34条からスピンオフしていった100を超える非営利法人のうち、なぜこの2つだけを取り上げるのか、後者はやや論理性に欠ける。そこでいっそのこと、今回の議論は現行の民法の公益法人だけに対象を限定しよう、という論者(注8)も出てくる。もっとも第一の立場だって、その他諸々の法人が傘下に馳せ参じるのは先の話。とりあえずは議論の対象を公益法人に限定しよう、ということになるとどれでもあまり変わらないという気がしないでもない。
税制上の取扱い
それでは何故こんなことにこだわった議論をしているかというと、税制上の優遇措置との関わりが非常に大きいからである。先にも述べたように、法人制度の話と税制上の取扱いの話は本来別な話である。法人制度の話は、憲法上の結社の自由から、組織運営上の継続性、あるいは持続可能性に至る様々な論点があり、法人として認められることのメリットに限っても、決して税制上の優遇措置に尽きるわけではない。しかし、公益法人はこれまで法人格取得と同時に税制上のメリットを享受してきた。それが今度は「法人は」「一般的に納税義務」がある。優遇措置があるのは「一定の場合」に限ることになる(注9)と、とにかく税金を取ってやろうという立場からは、その「一定の場合」をできるだけ狭く絞ろうとするし、逆に市民社会万歳派は、なんとか広く、できればこれまでに近い形での「範疇」としてそれを定めたいと考える。
非営利でありさえすれば税制上の優遇措置の対象になるのか、それでは足りず、「公益」あるいは「社会貢献性」といった概念を付加しなければならないか。これだけだって議論が紛糾しようというものだ。さらに税制上の措置といっても、所得税制と寄付税制の2つがあり、それぞれについて優遇の論拠、あるいは対象とされるべき組織の性格が必ずしも一致するとは限らない。それを一緒くたにして議論すると収拾し難いことになる。何が問題か。その所在を列記すれば以下とおりである。
まず所得に対する課税について。それが自分のために使われるから、つまり利益配分をするから課税するのではないか。だとすれば、利益配分をしない、つまり非営利組織の所得に課税する根拠はない、という考え方がある。この考え方に対しては、非営利組織でさえあれば、鉄鋼業でもタクシー業を営んでも所得課税はしないのか。一向にそれで構わないとするか(注10)、それではあまりにも広すぎるとして、通常「世のため人のため」と観念される分野的な制限(国際交流・環境保護・動物愛護等の例示列記)を加えるか。あるいは分野限定のみならず、非営利のうち、「公益」目的のものと然らざるものを分けて考えようとするか。さらにこれらすべての議論が、オール・オア・ナッシングなのか、「公益」性の強弱に応じて何段階かに分ける議論が可能なのか、という論点もある。
上記のどの考え方を取るか、というのはここでは論じない。どの考え方であれ、一長一短・利害得失はあるから、それは大いに議論を尽くせばよい。畢竟民間非営利組織の活動を如何に重要であると考えるか、考えないか、という問題と、税制上の公平性、均霑性との調和点の問題である。徴税技術論に堕することなく、「この国のかたち」を決めるという視点から衆知を集めた公開の議論をしてゆけば、落ち着くところに落ち着くであろう(注11) 。それよりも、何らかの優遇措置を適用した後に発生すると言われている問題点(ということは、だから安易に優遇措置を考えてはいけませんよ、という論拠の1つ)をここでは検討しておきたい。
その1:懸念の数々
まず第一に、その組織が所得をどんどん溜め込んだらどうなるか。つまり、世のため人のために使うわけでもなく、役職員に目を剥くような給料を払うわけでもないが(注12)、ただひたすらに所得を蓄積したらどうなるか(いわゆる「内部留保」の問題である)。別にそれはそれで構わない、と考えるか、それとも他日、本来目的のために使われるかもしれないとはいえ、やたらに蓄積されるのは不健全だと考えるか。「やたら」かどうか、どこでどのように線を引くか。いわゆる神学論争に堕することなく、操作的・実践的に問い掛けてゆけば、解決の方策は自ずから明らかになる。
財団法人については、基金運用収入の一定率を事業に用いるべきこととする(注13)。社団法人については、不測の事態による解散に備えて、数年分の事業費程度の蓄積は認めるものの、それを超えた分は課税対象にすればよい。
さらには、溜め込んだ挙句に法人を解散して、メンバーで山分けしたらどうなるか。それは許されない、というのが解散時財産分与の禁止である。しかし、余所様から組織の主旨に賛同して寄付を頂いているならいざ知らず、会員が払った毎年の会費に使い残しが出て溜めてあったのを、解散時に分配して何が悪いのか、という声も出そうである。いざ知らず、というのは溜め込んだオカネに寄付が含まれている場合の話で、善意の寄付者から頂いた分を、皆で分けてしまってはまずかろう。これについては後に触れる。
その2:いまひとつ所得の話
所得の話はもう1つある。ある法人の「本来の」事業と然らざるものを分けて考える必要があるのではないか。つまり、身障者の雇用創出を目的としてパン屋さんを開くのと、地球温暖化反対キャンペーンの財源獲得のためにパン屋さんを開くのは区別して考えるべきではないかという議論である。現在の税制はこれを区別しない。本来事業であろうがなかろうが、収益事業は一視同仁で扱っている。それでよいのか、という議論であり、これによれば前者は当然優遇措置の対象になるのに比して、後者は一般企業なみ課税で当然だ、ということになる。ここでいう「本来の」の意味は、先に述べた優遇措置を受けられるような「一定の場合」のことである。
ちなみに、会員制組織の会費収入はどうか。これが「本来の」収入であることは疑いない。会員制組織の会費であっても「一般的に納税義務」があるから、使い切らない限り課税しろ、という意見がないではない。さすがにそれはないよ、という結論になれば収益事業についてのみ「本来」事業かどうかの議論をすればよいということになる。これには異論もあり、「本来」事業か否かの煩雑な議論をしなくとも、上記身障者雇用等の社会福祉目的による政策非課税は、現行法制度のように個別に税法で決めてゆけばよい、とする。
その3:寄付の話
非営利法人に対する寄付について、現在の税制とその運用が、寄付適格の法人を極めて制限的に解しているのはよく知られている(注14)。これを拡大すべきだ、それが望ましいという声は高いし、筆者も全く同感であるが、それは論じない。ここでは寄付に対する税制上の優遇措置は所与であるとして、寄付を受けるほうの法人をめぐる2つの問題点だけに限定する。ちなみに、ここで法人というのは、改めて断るまでもなく非営利法人のことである。
1つは、先にも触れたが、その法人が解散時に財産分与をしてよいか、というもの。これは否定的に解するのが当然であろう。逆に言えば、寄付税制優遇の対象になるのは、解散時財産非分配の法人に限ると考えるべきである。
第2には、それならば解散時財産非分配の法人はすべて優遇対象になるのか。それともさらに何らかの「公益」性を求めるか、ということ。この場合、時代により場所によって様々に変化する「公益」を内容・実質に着目して定義しようとする一種の呪縛から離れて、非営利組織のうち、「専ら組織構成員の福利の向上に関心のあるもの」を除き、後はすべて公益目的と解する、というのも有力な考え方なように思う。これは税制上の取扱いを離れて「公益」とは何ぞやという神学論争に陥る愚を避ける意味もあるのは附言するまでもないだろう。
逆に、税制を離れて「公益」性の有無を論ずることに意義を見出す人も少なくない。詳論は避けるが、この立場からは事業の公益性の有無は税制のみに関わり、したがってその判断は課税当局に委ねられる、ということに断然反対の声が起きる。ことは志に関わり、志の有無を税務署に判断されるなどは論外だというものである。私見からは、この議論こそは説得定義(persuasive definition(注15)) の一典型例を提供するに過ぎないと思われるが、これまた詳論しない。
その4:財団法人の在否
他の点では限りなく曖昧な閣議決定の中で、一項だけ唐突かつ具体的に「財団については」「その在り方を検討する」こととされている。この項目が挿入された理由については想像の域を出ないが、幾つかの可能性があるように思われる。
第一は徴税側の論理である。財産だけを分離して、独立した法人にすることが準則主義で可能になるなんてとんでもない。狙いを付けた徴税の対象が、すっぽり別人格になるのを許しては、脱税、節税思いのままになるではないか。これは阻止しなくてはならない、というもの。
さらに、社団法人は株式会社でいえば株主総会にあたる社員総会があり、理事会の専横に対するチェック機能がある。それに引き替え財団法人は理事会に対する内部牽制機能がない。評議員会の設置程度では有効に機能するとは思われない。法人のガバナンス、アカウンタビリティという見地からも、こんな非民主的な組織は存置すべきではない、という理由も付いて来る。
治安維持法の予防検束ではあるまいし、最悪の事態を想定してそれができないような制度設計を行う、というのは感心した態度ではない。現行の指導監督体制がその1つであることはもう繰り返さない。最低限のしてはいけないこと、禁止さるべきことを法定し、それ以外は自由である、というのは罪刑法定主義の基本だし、近代法の精神でもある。
仮に税金を取り損なったからと言って、できた財団法人が世のため人のためになることをするのならそれは結構な話(注16)だし、仮に何もしなくても、別に設立者がそれで得をする訳でもない(注17)。逆に先にも述べたように、一定支出を義務づければそれに違反して課税されるだけの話である。
それに比べて、後者のいい分には一理ある。しかし、理事会の専横の危険性ということは、反面、即断即決の利点もある、ということだ。事業の継続性と柔軟性を両立させるのは、言うは易く行うは難い。組織ガバナンスは奉仕する利益とステークホルダーによって柔軟であってよいのではないか。最低限のアカウンタビリティは情報公開によって担保する、という考え方こそ、人類の歴史的叡智の産物である財団法人にはふさわしい。
むしろ、基本財産運用益によって活動をする、という本来の主旨からは遠いミニ財団が多い現状(注18)から、そうしたものを公益信託に移行させると同時に、公益信託にも法人格を与える、という方向での検討こそ望ましいのではないか。
淘汰は可能か
最後に、既存公益法人の中から「世のため人のため」に機能しているとは言い難いものをどう選び出して淘汰するか、という難題が残る。これに該当すると思われる類型はいくつかあるが、例えば
- かつては公益的であったかもしれないが、現在は営利企業であるか、特に税制上の優遇措置を付与されるに相当しないもの。
- 行っている事業にほとんど今日的な意義がなく、漫然と存在しているか、あるいは単に退職後の官僚の就職先と化しているもの。
- 設立目的と明らかに背馳した事業内容が常態化しているもの。
などが代表的なものではないか。公益法人の緒言については悉皆調査が行われており、すべて主務官庁が把握している(筈である!)。まずこうした範疇に属するものと思われる法人を主務官庁に選定させ、公示することから始めるのが現実的であろう。諸悪の根源の一翼を担ってきた主務官庁にとっては、名誉回復の絶好の機会となることも期待される。それがあまりにも現実離れした期待であるというのならば、これと平行して公益法人の側からも自浄作用としての基準作りも行われなければなるまい。
終わりに
この種作業、あるいは「公益性」認定のために第三者機関を設置してはどうかという意見をよく耳にする。もちろん悪い話ではないし、一部地方自治体に見られるように、理想的に運営されれば1つの解決策ではあろう(注19)。ただ、既存のいわゆる第三者機関、あるいは諮問機関なるものの実態を見ると、あまり楽観的になれないのも事実である。それよりは国際的な企業の社会的責任(CSR)プログラムなどに見られる、徹底した情報開示の効果を期待する(注20)ほうが実りは大きいのではないか、というのが私見である。
- 例えばC's ニュースレター第44号、p.3、2003.7.23
- http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/gijiroku/hwg001.htm~
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/gijiroku/hwg006.htm - 2003.6.29付毎日新聞朝刊社説、また同年.11.26付なごやボランティア・NPOセンターにおける今田日本NPO学会会長講演タイトルの一部
- 「経済産業省は外郭団体の宇宙実験システム研究開発機構が・・・」(2003.10.20付日本経済新聞朝刊p.23)、「厚労省外郭団体が調査 厚生労働省の外郭団体、医療経済研究機構」(2003.11.5付日本経済新聞朝刊p.38)はその一例。
- その1つが宗教法人を検討の俎上にあげることである。連立政権政党の1つである公明党の支持基盤、創価学会との関係を巡って、政府にこれを取り上げる可能性があるかどうかを指摘する向きも少なくなかった。
- 拙著「日本の公益法人」、ぎょうせい、2003の立場はこれに近い。
- 「シンクネット・構想日本」の立場はこれに近い。http://www.kosonippon.org/
- (財)公益法人協会の立場はこれに近い。http://www.kohokyo.or.jp/
- ちなみにこの立場は何も事新たなものではなく、これまでと何の変りもない、と考えることも可能である。税法上の有利な地位は「税法が個々に与えているものであって、法律上そのようになる必然性はない」(星野英一『民法のすすめ』、岩波書店 p.94、1998年)からである。あたかも準則主義と原則(非)課税がトレードオフの関係にあるような議論(NPOサポートセンター連絡会監修『NPO・公益法人改革の罠 -- 市民社会(シビルソサエティ)への提言』、p.68の石村耕治発言、第一書林、2003年)はミスリーディングであろう。
- 非営利では投資家を集められない。そこで自動的に歯止め掛かる、と考える。
- 税の逋脱を恐れたり、税収確保を重視する立場もあれば、市民社会組織の活動強化を希む立場もある。それぞれが公開の席で大いに議論する態度が望ましい。その意味では先の税調の非営利法人課税ワーキング・グループの中にあって、民間非営利の立場から論陣を張った堀田力氏を平成15年10月、突然メンバーから外した態度はフェアであるとは言い難い。
- 定義的に非営利、すなわち利益非配分に抵触する。
- 例えば、プライム・レート相当分。使わなかった場合にはペナルティを課する。米国の義務的give awayと同じ。
- 例えば、特定公益増進法人の場合、法人税法施行令77条1項三号政令第3号の公益法人は僅か818法人(2003.4)である。
- 情緒的な価値判断を含む言葉を定義として用いること。読者を特定の方向に説得するために用いられる。「彼は真の芸術家ではない」は一例。
- 「日本は累進課税がきついからそんなことはできないだろうが、ビル・ゲイツやテッド・ターナーみたいな日本人が現れて、ポンと何百億円かの財団を作られたりしたら口惜しくて夜も眠れないだろうな。ああ、相続税を取り損なった」というのが徴税側の意見である。果たして一般の支持を受けるだろうか。
- 出来の悪い子供をその財団の役員にして高給を払ったりできるではないか、という説もある。そこまで気を回す必要があるのだろうか。むしろ明らかに税の逋脱を目的として設立されたものは、遡求的に設立取消しができるとでもしたほうが合理的ではないか。
- 基本財産5千万円以下のものが全体の6割近い。(平成15年度版公益法人白書 p.38)
- これを民間機関とするか、公務員にするかは議論が分かれるが、仮に公務員であっても、現在中央・地方で公益法人許可・指導監督に当たっている定員をまとめれば不可能ではない。
- GRI(Global Reporting Initiative)はその一例である。