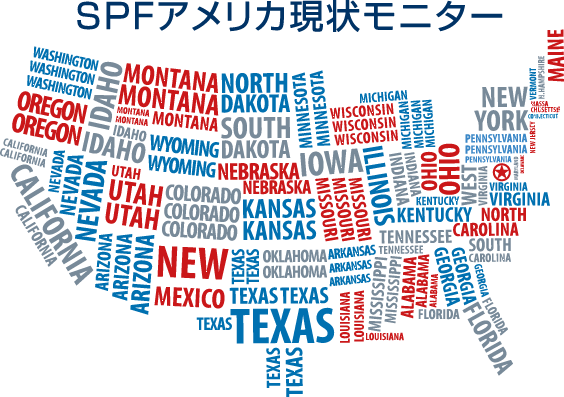アメリカをめぐる4つのナラティブと国際主義

中山 俊宏
『イラク戦争のアメリカ(The Assassin’s Gate: America in Iraq)』(2005年)や『綻びゆくアメリカ(The Unwinding: An Inner History of the New America)』(2013年)を著したジョージ・パッカーが近著『最後にして最善の希望(Last Best Hope: America in Crisis and Renewal)』(2021年)において描くアメリカは、交差することのない4つのアメリカの姿だ。近年、アメリカにおいて対立が描かれる時、それは保守とリベラルの対立として描かれてきた。そこには明確な対立があった。しかし、パッカーの描くアメリカは、すれ違うアメリカだ1。
保守とリベラルの対立は、「ありうべきアメリカの姿」をめぐる対立だった。それは、アメリカのあるべき本来の姿をめぐる対立であり、エリック・フォーナーはそれを二つの「自由をめぐる物語(The Story of American Freedom)」として語った。それは、アメリカを国家として成立させる理念をめぐる争いだった。しかし今のアメリカは、こうした共同性そのものがもはや成立不可能ではないかという深淵を覗き込んでいる。この深淵は、トランプによって白日の下に曝されたが、それはトランプが引き起こした状況ではない。
パッカーは『イラク戦争のアメリカ』でイラクにおいて躓くアメリカを描き、『綻びゆくアメリカ』では「アメリカン・タペストリー(織物)」が綻んでゆく様子を描いた。2つの作品は、アメリカをアメリカたらしめていた物語が内と外で破綻していく様子を描いたものだった。パッカーの著作で印象的なのは、その様子を声高な予言者のように騒ぎ立てるのではなく、淡々と語っていることだ。『綻びゆくアメリカ』では、その様子を、彼が出会ったごく普通のアメリカの人々に語らせている。それは期せずして、「トランプ」を生み出したアメリカの心象風景にもなっている。
パッカーが描く4つのアメリカは、それぞれ「フリー・アメリカ」「リアル・アメリカ」「スマート・アメリカ」「ジャスト・アメリカ」だ。パッカーはそれを、アメリカを意味づける4つのナラティブと呼んでいる(この4つのアメリカについては、新型コロナ危機との関連で、最近別稿2でも論じたので、そちらも参照されたい)。
まずは「フリー・アメリカ」だ。これはレーガンによって体現される、いわばアメリカにおける「保守本流」だ。冷戦時代、「自由世界(フリー・ワールド)」という言葉は特殊な響きを帯びていた。それは文明世界の主流をめぐる争いというニュアンスを含んだ言葉であり、アメリカに対する揺るぎない自信が「フリー・アメリカ」のナラティブを支えていた。しかし、冷戦の終焉とともに、「フリー」の意味合いが変化し、文明史的なニュアンスは希薄化していく。そして、もともとあった連邦政府による恣意的な介入からの自由という方向に大きく傾斜し、「放っておいてくれ(leave-us-alone)」という衝動に突き動かされる、「消極的自由」の原理的な追求に堕してしまった感がある。
「フリー・アメリカ」は、アメリカが存在する限り、なくなることはないだろう。しかし、それはもはやアメリカが直面する状況に対する解を提示しえていない恐竜のような存在になりつつある。
「リアル・アメリカ」は、人種構成、産業構造の変動、情け容赦なく進む世俗化など、アメリカで進展する変化に適応できない、もしくはそうした動きを拒絶する、ホワイト・クリスチャン・ナショナリズムに根を下ろすナラティブである。クリスチャン・ナショナリズムは、星条旗とキリスト教信仰が完全に重なり合うような思考で、この空間における「アメリカ」は、レーガンが思い描いていたような「フリー・アメリカ」で想定されていた「アメリカ」とは本質的に異なる。それは「土着的なアメリカ」であり、「世界を変えていこうとするアメリカ」ではなく、「世界によって変えられることを恐れるアメリカ」である。「リアル・アメリカ」は、2008年に共和党の副大統領候補だったサラ・ペイリンによって体現される。その延長線上に、ティーパーティー運動、トランプ現象などを定置できるだろう。それは、変化に対する剥き出しの敵意が政治空間に流入する経路を確立した。「リアル・アメリカ」は、人種主義、孤立主義、そしてナショナリズムと信仰心が綯い交ぜになった「反動的なアメリカ」でもある。トランプ以降、共和党において支配的なナラティブの地位を確立しつつあり、「フリー・アメリカ」とは相容れない存在である。共和党の中でトランプ路線に反対を表明するリズ・チェイニー下院議員の孤軍奮闘ぶりが、「フリー・アメリカ」が置かれている状況を象徴しているといえよう。
「スマート・アメリカ」と「ジャスト・アメリカ」は、保守−リベラルの座標軸の上では、リベラルの側に位置づけられるが、両者の間に共通言語はないという点では、「フリー・アメリカ」と「リアル・アメリカ」の関係に似ている。現在は、民主党がホワイトハウスと連邦議会という権力の要所を抑えているので、亀裂は目立ちはしないものの、潜在的には「グローバル・エリート」と社会的弱者・マイノリティの対立を内に含んでおり、ここの対立は深刻だ。「スマート」と「ジャスト(正義)」という用語だけを見ると、ポジティブな意味合いを持つような印象を受けるが、パッカーの批判は厳しい。
「スマート・アメリカ」は、アメリカの変化にもっとも馴染んでいるエリート大学卒の都市郊外に住むプロフェッショナル・クラスである。メリトクラシーの原則の下、競争を勝ち抜いてきた人たちによって構成されるが、もはやそれは「階級」の感をなし、「スマート・アメリカ」の外で育った子供たちが、このグループに入ることはますます難しくなっている。この層の最大の問題は、「スマート・アメリカ」の循環的再生産だ。しかし、競争を勝ち抜いてきただけに、自らの存在に対する正当性の感覚が強い。アイビー・リーグの大学の卒業証書が最重要の価値を持つようなグループだ。「スマート・アメリカ」で育った子供たちは、当然の権利であるかのように、「スマート・アメリカ」に再吸収されていく。この「スマート・アメリカ」の帰属意識は、アメリカそのものにあるというよりも、自分たちの階級の循環的再生産を可能にさせるような「コスモポリタンな世界」である。おそらく、変化するアメリカの中でも難なく生き残っていけるであろうオバマが、スマート・アメリカを最も象徴的に体現しているだろう。「スマート・アメリカ」におけるアメリカは、「自由世界」を支えるアメリカでもなく、土着的なアメリカでもなく、ツルッとした「のっぺらぼう」なアメリカである。トーマス・フリードマンが、かつて来るべき世界を「フラットな世界」と評したが、期せずして、オバマがアメリカの「例外性」を否定したことが、「スマート・アメリカ」のコスモポリタンな世界観と合致している。
同時にオバマは、初のアフリカ系大統領として、片足を「ジャスト・アメリカ」の方に突っ込んではいる。しかし、「ジャスト・アメリカ」はある意味、ポスト・オバマ的な現象である。それは、「初のアフリカ系の大統領」の誕生をもってしても、乗り越えられないアメリカの「原罪」をめぐるナラティブである。アメリカの「正史」を、奴隷制を軸に読み変えていこうとする「1619プロジェクト」3がその典型だ。「ジャスト・アメリカ」は、これまでアメリカが蓄積してきた不正義を、先鋭的な「ジャスティス(正義)」の感覚でもって「矯正」していこうとする立場である。特に若い世代、ミレニアル世代やZ世代に共有されるナラティブで、これまでのアメリカン・ストーリーの中に居場所を見出せず、上の世代のようなアメリカ人としての成功体験をしておらず、「スマート・アメリカ」にも参入できないグループに受け入れられた。近年は、「ウォーク(woke)4」や「キャンセル・カルチャー」という言葉とともに語られる潮流だ。「オバマという希望」が未完に終わったあと勢いづき、白人警官によるアフリカ系アメリカ人に対する暴力の告発をきっかけに一気に加速した。そこに、ジェンダー、気候変動、格差問題なども重なり合い、その主張の「正しさ」ゆえに、「不寛容な正義」という方向に向かう危険性を常に内包している。トランプの存在が、「ジャスティス派」の「正しさ」を確信させ、「不寛容な正義」という傾向を加速させた。彼らの告発は、「フリー・アメリカ」と「リアル・アメリカ」に対して向けられるが、「スマート・アメリカ」に対しても手厳しい。格差問題が、もはや「フリー・アメリカ」のみに帰せられる問題ではなく、「スマート・アメリカ」もその責任の一端を担っているからだ。
「ジャスト・アメリカ」は運動体なので、この潮流を誰か一人に象徴させることは難しいが、あえてそうするならばニューヨーク州選出の下院議員、アレクサンドリア・オカシオ=コルテス(AOC)だろう。動きとしては、1619プロジェクトを挙げてもいいかもしれない。
そうなると現在のアメリカは、レーガンのアメリカ、ペイリンのアメリカ、オバマのアメリカ、そしてAOCのアメリカが、それぞれ交差することなく、互いに摩擦を引き起こしながら併存していることになる。そこには4つのアメリカを束ねる共通のナラティブはない。亀裂は前二者対後二者の間だけではなく、場合によっては前二者と後二者それぞれの内部の亀裂の方が深刻かもしれない。ともするとトランプと「リアル・アメリカ」を重ねて見がちだし、確かに「リアル・アメリカ」とトランプの親和性は高いが、むしろトランプは共通のナラティブが不在であるという状況そのもの、つまり理念国家の中心が虚空であるがことが垣間見えた時に発生した反作用のような存在ではないか。
バイデンがどこに位置するかというと、これもなかなか難しい。バイデンは、民主党でありながら、「スマート・アメリカ」とも「ジャスト・アメリカ」とも完全には重ならない。前者には厳しく、後者には擦り寄っていきつつも、同化はしていない。さらに排外主義的な要素を抜き去った「リアル・アメリカ」との親和性があることも否定できない。「ミドルクラス外交」や「バイ・アメリカン」がそれにあたる。旧世代のバイデンは、むしろ「オールド・リベラル」であり、この4つのナラティブの混合形態であることが、その強みであると評価することも可能だろう。しかし、「バイデン」という現象は、あくまでバイデンという固有の人物に依拠したものであり、4つのナラティブのすれ違いを超克する5つ目のナラティブを形成しているとは考えにくい。バイデン・ナラティブの「再生産」は容易ではないだろう。
では、この4つのアメリカをめぐるナラティブが世界と向き合った時にどのような化学反応を引き起こすのだろうか。まず大前提として、冷戦期に形成された国際主義をめぐるコンセンサスが脆弱な状態にあることについては、異論はないだろう。これがある意味、共通項だ。外交安全保障エスタブリッシュメントは、引き続きアメリカの国際的な関与を主張し続けるだろうが、アメリカ国民の間にそうした立場を支える機運はない。確かに中国(そしてロシア)との大国間競争の時代に移行しつつあるという認識は広がりつつも、冷戦期の「反共コンセンサス」のような国民を巻き込んだ大きな合意は形成しえてない。むしろ、世界は「アメリカ後の世界」に突入しつつあるという漠然とした予感が共有されるなか、おそらくアメリカが初めて向き合う「同格の競争相手(peer competitor)」とどう対峙していくのか、この「長い競争(long competition)」を果たして本当に続けていくことができるのか、迷いつつも、ギアを上げているというのが現状だろう。
4つのナラティブごとに見ていこう。まず「フリー・アメリカ」は、レーガン的な世界観を引き続き保持しつつも、世界をつくり変えていこうとする意志を欠くアメリカという現実に直面せざるをえない。「フリー・アメリカ」は、これまで一貫して「前傾姿勢の力強い国際主義(forward-leaning-muscular-internationalism)」を支えてきた。しかし、ネオコンの退潮に象徴されるように、もはやアメリカはレーガン的なリーダーシップを発揮する意志と体力を欠いている。パッカーは、「フリー・アメリカ」の対外政策は、アメリカ社会のロジックをそのまま外の世界に対して投射したものだと論じている。その関連でいえば、「リアル・アメリカ」は外の世界を変えることではなく、「外の世界に変えられること」をただひたすら嫌悪し、「スマート・アメリカ」はアメリカが「外の世界に適応していくこと」を最重要視する。「ジャスト・アメリカ」は、アメリカの国内的な原罪を告発することにかかりっきりで、アメリカの国際的な負担を減らしていくこと以外には関心は向かわない。「ジャスト・アメリカ」も、その「閉鎖的気分」ということに関していえば、「リアル・アメリカ」に負けていない。唯一重要な例外が、「ジャスト・アメリカ」が実存的脅威と捉える「気候変動」に関するコミットメントだろう。なお、「フリー・アメリカ」内部にも、「リバタリアン的潮流」が存在し、これはアメリカの国際的な役割を最小化することを企図する動きであり、連邦政府への「イデオロギー的不信感」の延長線上にある国際関与への不信感という点において、実は「リアル・アメリカ」と親和性が高い。
では、「リアル・アメリカ」はどうか。「リアル・アメリカ」は、アメリカを世界に引きずり出そうとする対外政策エリートへの不信感によって特徴づけられている。「もういい加減、グローバルな責任は放棄しよう」という気分だ。ただし、ガズデン旗5に象徴されるように、自分の領域内に異物が侵入してきたと見なすや、その攻撃性は一気に高まる。「リアル・アメリカ」の中国に対する「敵意」は、このあたりに起因していると見るべきだろう。このため、目の前の脅威に対しては牙を剥きつつも、その脅威に対して恒常的に圧力をかけ続け、それをより効果的に行うための同盟国、パートナー国との連携、そして西側にとって有利な秩序を支えるリーダーシップを期待できるかという点については、大きな疑問が残るといわざるをえない。
「スマート・アメリカ」は「コスモポリタン・アメリカ」と言い換えてもいいくらい国際派である。しかし、それはアメリカの力に依拠した国際主義ではない。世界が繋がっていくことそのものを良しとし、それを支えるのが「スマート・アメリカ」のナラティブである。ナショナルな感覚は希薄で、「グローバル・エリート」によって構成される世界が、アメリカにとってもより好ましいという認識に依拠している。グローバルな啓蒙主義と言い換えられなくもないが、すでに言及したように「グローバル・エリート・クラス」の循環的再生産がこのナラティブ最大の副産物だろう。そこにはアメリカを束ねられる国際主義のロジックはなく、トランプの「アメリカ・ファースト」がそのことを白日の下に曝した。
最後に「ジャスト・アメリカ」だが、このナラティブは、そもそも「アメリカの使命」に強い不信感を抱いている。もっぱら国内の問題に捉われ、国際情勢には不思議なほど無関心だ。時としてパレスチナ問題など、ピンポイントで関心が向けられるが、「正義の感覚」に基づいてアメリカの対外政策を再構成するというような本格的な動きは見られない6。それもそのはずで、アメリカという国の正統性を告発することに主たる関心を寄せる彼らが、世界を作り替えようと世界に身を乗り出していこうとはしないことは明らかだ。
こう見ると、パッカーが描く4つのアメリカをめぐるナラティブはいずれも、かつてアメリカが引き受けていたような国際主義を支えるストーリーを紡ぎ出すことができていない。それぞれが、異なった「世界」を認識し、その認識が重なり合うことがないまま、退潮傾向を後押しするような状況を加速させている。対外政策についての認識も重なり合わず、もはやアメリカの国際主義を突き動かしてきた使命的民主主義を支えるストーリーが不在である。この事実は、これから本格的に大国間競争の時代に突入していくアメリカにどのような影響を及ぼすのだろうか。
一般的には、アメリカは中国との戦略的競争(そして潜在的には対決)に向けて準備を整えつつあると評されることが多い。それはそれで間違いない傾向だろう。現に、中国の露骨な覇権的野望が、4つのナラティブを統合する可能性は否定はできない。「フリー・アメリカ」は、中国からの地政学的挑戦を受けるなかで、その「力強さ」を取り戻し、「リアル・アメリカ」は中国への敵意を先鋭化させ、「スマート・アメリカ」は中国を「可能性」よりはむしろ「弊害」と見なすようになり、「ジャスト・アメリカ」も価値の領域で中国を好ましからざる存在として認識するに至るという具合だ。しかし、米中対立をめぐるレトリックとは若干別の位相で進行しつつある、アメリカの自己認識との関連で意味づけられるアメリカの国際主義の様相は、そんなに盤石なものではないことも事実だろう。この辺りの動きが、どう政策や政治に反映していくのかを見極めることも重要だろう。
この関連で最後に述べることがあるとすれば、本稿で見てきたように、アメリカの国際主義を支える基盤は磐石ではないものの、いざ具体的な脅威に晒された時、アメリカは衝動的に拳を振り上げ介入していく可能性もある、ということを認識しておかなければならないということだ。それは、「もう国際的関与を減らしていった方がいい」というアメリカの自己意識と、そうした傾向を認識する国際社会の側のアメリカについての心象(介入しないアメリカ)にもかかわらず、これらと矛盾する動きをアメリカがとる可能性が十分にあるということだ。その期待と結果のギャップの存在こそが、国際社会の不安定要因を増大させているという見方もできるだろう。
(了)
- George Packer, The Assassin’s Gate: America in Iraq (Farrar Straus & Giroux,2005)
邦訳:『イラク戦争のアメリカ』(豊田英子訳、みすず書房、2008年)
George Packer, The Unwinding: An Inner History of the New America(Farrar Straus & Giroux 2013)
邦訳:『綻びゆくアメリカ』(須川綾子訳、NHK出版、2014年)
George Packer, Last Best Hope: America in Crisis and Renewal(2021)
※本文中の『最後にして最善の希望』の訳は筆者(本文に戻る) - 中山俊宏「新型コロナ危機と四つのアメリカ」『国際経済連携推進センター』2021年7月21日(2021年8月3日参照)(本文に戻る)
- 1619プロジェクト<https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html>(2021年8月3日参照)(本文に戻る)
- woke/woke leftについては、渡辺将人「『ウォール街選挙運動2.0』としてのBLM:『新世代左派』と民主党の内紛危機」を参照(本文に戻る)
- ガスデン旗/Gasden flag <https://en.wikipedia.org/wiki/Gadsden_flag>(2021年8月3日参照)(本文に戻る)
- 「正義の感覚」に基づいてアメリカの対外政策を再構成するというような動きがないわけではない。例えば、Just Foreign Policy(https://www.justforeignpolicy.org)というような動きがあるが、アメリカの対外政策に対する影響力は限定的だ。(本文に戻る)